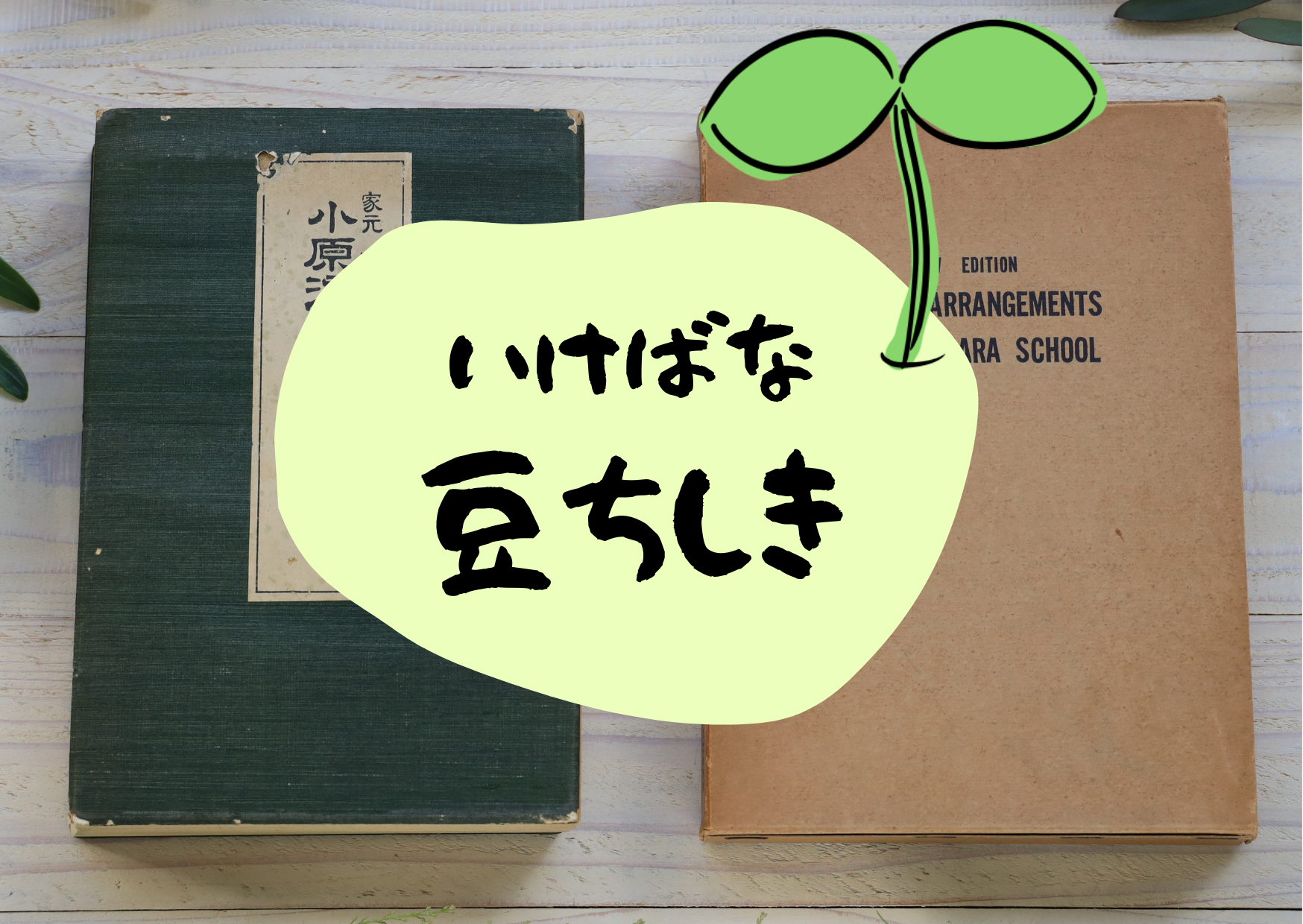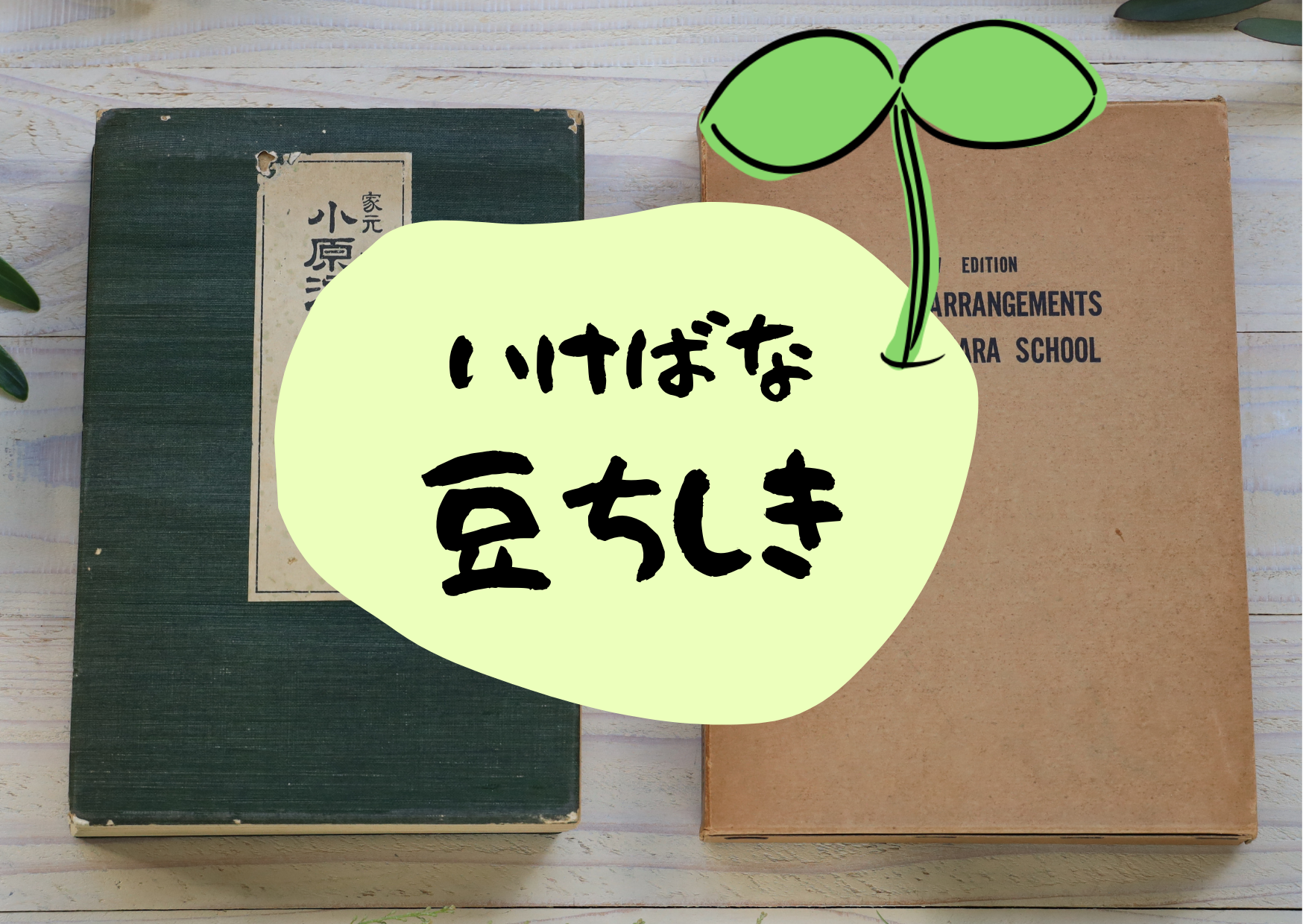いけばな豆知識 vol.04 【造形いけばな】
本コーナーでは知っているとちょっと嬉しい、いけばなの豆ちしきを不定期でご紹介しています。
2022年9月号は「造形いけばな」をご紹介いたします!
小原流の花展に限らず、他流派、諸流派の花展でも必ず目にする「造形いけばな」。
しかし普段のお稽古で学ぶ方はあまりいないのではないでしょうか。
「これっていけばななの?」と思う方も少なくないはずです。
いけばな研究家・工藤昌伸先生の過去のインタビュー記事を紹介いたします。
いけばなで「造形」という場合、その意味は素材および花器、型に対して制約のないいけばなということになるでしょう。。
言うまでもなく、通常、お稽古などでいけられるいけばなも一つの「造形物」。
「造形物」には違いないけれど、素材やいけ方、器などに大きな制約があります。
ところが花展などに見る「造形いけばな」の作品には、会場のスペースや作品の大きさ以外の制約がありません。
制約を排除した方がより完全な造形に近付く、という考え方に基づいて制作されています。
またいけばなにおいては植物の持つ風情が重要視されますが、「造形」ではそれすらも制約としてとらえ、できる限り排除しようとするのです。
小原流挿花1993年特集「造形」ってなに?より抜粋
...ふむふむなるほど!と頭では理解できたつもりでも、様々な疑問が浮かぶのではないでしょうか。
「結局、造形いけばなって、なんでいけばななの?」
「現代美術作品とどう違うの?」
「いけばなを学ぶ人が造形いけばなに取り組むキッカケは?」
次月号の小原流の事務局報では、「造形いけばな」のそうした疑問について小原流東京支部名誉幹部の伊藤庭花先生と、小原流研究院教授の工藤亜美先生お話を伺います。
お二人は「新いけばな主義」に参加し、精力的に「造形いけばな」の作品発表を続けています。
動画での紹介を予定しておりますので、お楽しみに!
関連記事
新いけばな主義リレー個展開催のご案内(東京)
「これからのいけばなを考える会」運営委員の有志により開催されている「新いけばな主義リレー個展」。 そちらの花展に小原流から東京支部名誉幹部の伊藤庭花先生、研究院教授の工藤亜美先生が参加されています。 ※2022年7月号の記事です
詳しくはこちらから。
新いけばな主義リレー個展が開催されました(東京)
「これからのいけばなを考える会」運営委員の有志により開催されている「新いけばな主義リレー個展」。7月29日 -8月7日の最終会期、展示のアンカーは工藤亜美先生となりました。会場の様子をお届けいたします。
詳しくはこちらから。
(速報!)「北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI2022」家元作品制作風景!
9月17日(土)から開催される「北陸工芸の祭典 GO FOR KOGEI2022」に家元作品が展示されます。制作風景をいち早くお届けいたしますのでご覧ください。
詳しくはこちらから。